写真コンテスト
第59回 (2018年)
カメラ部門 受賞作品
グランプリ
「夜空に咲く大輪の花」
菅野 照晃 様

審査委員会コメント
準グランプリ
「夢幻華」
太田 征男 様

審査委員会コメント
露光間にフォーカスを移動する、「福田式」と言う技法による撮影でしょうか。
奥行、広がり、そして幻想的な美しさは言葉にできません。
サクランボ色をした水玉の散らばる中に、放射してゆく光輝が作り出すカエデに似た花が二輪生まれているのがとても不思議で魅力的です。
今回の入賞者中、もっともご高齢の作者ですが、その作品、感性の若々しさは随一のものです。
奥行、広がり、そして幻想的な美しさは言葉にできません。
サクランボ色をした水玉の散らばる中に、放射してゆく光輝が作り出すカエデに似た花が二輪生まれているのがとても不思議で魅力的です。
今回の入賞者中、もっともご高齢の作者ですが、その作品、感性の若々しさは随一のものです。
タニタ賞
「真夏の夢」
片桐 新一郎 様

審査委員会コメント
いたばし花火大会の会場を思い浮かべるとき、皆が頭に描くのはこの作品のような光景ではないでしょうか。
とこまでも続く観客席の提灯、目の前に開花する花火。
河川敷の拡がりゆえでしょうか、大玉の打ち上げにもどこか落ち着きがあるように思えます。
卓越した技術で捉えた美しい花火を、安定した構図の中にレイアウトした円熟の一枚です。
とこまでも続く観客席の提灯、目の前に開花する花火。
河川敷の拡がりゆえでしょうか、大玉の打ち上げにもどこか落ち着きがあるように思えます。
卓越した技術で捉えた美しい花火を、安定した構図の中にレイアウトした円熟の一枚です。
「光の蝶」
陳 剛 様

審査委員会コメント
「これは可憐な花に誘われて蜜を吸いに来た蝶の写真です。」と言われれば、はいそうですねとしか言いようがありませんがちょっと待ってくださいこれは花火の写真なんですよと。
その位、自然に、ありのままの美を写し取っている見事な作品。
さらに、技術的にもピント、露出、構図、すべてが完璧に決まって一切の破綻がありません。
人工の極致が自然に近付く、その見事な成功例です。
その位、自然に、ありのままの美を写し取っている見事な作品。
さらに、技術的にもピント、露出、構図、すべてが完璧に決まって一切の破綻がありません。
人工の極致が自然に近付く、その見事な成功例です。
「フルーツパフェ」
越部 諭 様

審査委員会コメント
タワーマンションを中心に色とりどりのフルーツが花を咲かせる、とてもカラフルで魅力的なスイーツ。
ピュアな感性の作者のこと、もちろんフルーツパフェに見立てたこの作品ですが、これが「フルーツ盛り合わせ」に見えた方はほんの少しの純真さを取り戻しましょう。
ご自宅からの撮影とのこと、何ともうらやましい限りの環境ですが、ぜひ会場でもカラフルな作品をものにしてください。
ピュアな感性の作者のこと、もちろんフルーツパフェに見立てたこの作品ですが、これが「フルーツ盛り合わせ」に見えた方はほんの少しの純真さを取り戻しましょう。
ご自宅からの撮影とのこと、何ともうらやましい限りの環境ですが、ぜひ会場でもカラフルな作品をものにしてください。
蒙古タンメン中本賞
「宇宙の花」
中谷 知里 様

審査委員会コメント
大ぶりの菊花か、はたまたダリヤか。圧巻の大迫力で宇宙に花開いたそのさまは、巨大なエネルギーを放出するゴールドに、その熱量を鎮めるべく寄り添う可憐なブルーの小花が画面を引き締め、作品をより格調高いものにしています。
複雑で混沌とした世界に調和がもたらされたその瞬間を映像化した驚異の作品がこの宇宙の花です。
複雑で混沌とした世界に調和がもたらされたその瞬間を映像化した驚異の作品がこの宇宙の花です。
「息をのむ美しさ」
杉本 春香 様

審査委員会コメント
今回の入賞作の中では珍しい、落ち着きある正統派の作品です。
3x2でなく、4x3でもなく、スクエアフォーマットでもなく、必要な要素だけに削ぎ落して構成した力強さと重厚感がこの作品の魅力です。
右下の小さな赤いハートと大玉のバランスが素晴らしく、ハートの周りのグリーンもこの小粋なアクセントを引き立てて画面全体を引き締める役割を担っています。
3x2でなく、4x3でもなく、スクエアフォーマットでもなく、必要な要素だけに削ぎ落して構成した力強さと重厚感がこの作品の魅力です。
右下の小さな赤いハートと大玉のバランスが素晴らしく、ハートの周りのグリーンもこの小粋なアクセントを引き立てて画面全体を引き締める役割を担っています。
チケットぴあ賞
「昭和スタイルの平成生まれ」
杉山 一樹 様

審査委員会コメント
とってもよく似たご兄弟ですね。好奇心と瞳の輝きに満ちたお二人の明るい表情も抜群に魅力的ですが、弟さんが「な?ここの花火はひと味違うだろ?」「この一発を見せたかったんだよ!」とでも言ってそうな、お兄さんの肩に回した左手が、この一枚の楽しさを5割増しにしています。
同席のご家族、後列の座席のグループ、土手の客席と、重層的な構成も面白く、引き込まれる作品です。
同席のご家族、後列の座席のグループ、土手の客席と、重層的な構成も面白く、引き込まれる作品です。
「木の後ろで」
木下 祐紀子 様

審査委員会コメント
観覧席からの視界に入り込んだ一本の樹。鑑賞のためには妨げにもなるこの存在を、木下さんは独自のイマジネーションによって作品の立役者に変えました。
河川敷を利用して行われるいたばし花火大会は、環境保護の観点から極力自然に手を付けずに行うことを旨としています。
この樹に関しても様々に議論がなされていますが、白銀に輝く花火を背景に、“シルエット”としての魅力を浮き出させた構成力には、主催者としてひとまず頭の下がる思いです。
河川敷を利用して行われるいたばし花火大会は、環境保護の観点から極力自然に手を付けずに行うことを旨としています。
この樹に関しても様々に議論がなされていますが、白銀に輝く花火を背景に、“シルエット”としての魅力を浮き出させた構成力には、主催者としてひとまず頭の下がる思いです。
「待ってました!!」
瀬戸 健太郎 様

審査委員会コメント
今年の大会では、ナイアガラの滝と尺五寸玉のコラボレーションが実現しましたが、皆さまお楽しみいただけましたでしょうか。
そんな大会のハイライトを作品にしてくださった瀬戸さんのこの一枚、左下の人物の写り込みがピリッと効いていますね。
長秒時露光ゆえナイアガラの滝は氷結した大瀑布の如き塊となりましたが、繊細に描写された尺五寸玉が好対照となりドラマ性を高めています。審査委員はこんな作品の登場を「待ってました!!」
そんな大会のハイライトを作品にしてくださった瀬戸さんのこの一枚、左下の人物の写り込みがピリッと効いていますね。
長秒時露光ゆえナイアガラの滝は氷結した大瀑布の如き塊となりましたが、繊細に描写された尺五寸玉が好対照となりドラマ性を高めています。審査委員はこんな作品の登場を「待ってました!!」
板橋のいっぴん賞
「夢うつつ」
堀田 純 様

審査委員会コメント
ご常連の堀田さんがまたまた入賞をものにしました。きりっとコントラストの高いシティスケープと、敢えてアウトフォーカスした大玉花火や水玉状の光を組み合わせ、幻想的で味わい深い花火写真に仕上げました。
センターを外した構図により生まれた左側の空に、ほのかな気配を漂わせる花火とのコントラストが作り出す深い余韻を感じさせます。
センターを外した構図により生まれた左側の空に、ほのかな気配を漂わせる花火とのコントラストが作り出す深い余韻を感じさせます。
「競演」
竹内 正憲 様

審査委員会コメント
いたばし花火大会の中でもとりわけ人気の高い、「花火の鉄人、芸術玉の競演!」。
この作品は、日本最高峰の花火職人入魂の一発を、10人分まとめて一つの写真にしてしまおうと言う、大胆不敵にして崇高な試みにチャレンジした傑作です。
あの夜、目を凝らして追った銘玉その一発一発の感動が蘇ります。
抑制の効いた露出と相まって、アルティザンでありアーティストである花火職人の情熱が浮き上がって来るようです。
この作品は、日本最高峰の花火職人入魂の一発を、10人分まとめて一つの写真にしてしまおうと言う、大胆不敵にして崇高な試みにチャレンジした傑作です。
あの夜、目を凝らして追った銘玉その一発一発の感動が蘇ります。
抑制の効いた露出と相まって、アルティザンでありアーティストである花火職人の情熱が浮き上がって来るようです。
「華」
杉 稚菜 様

審査委員会コメント
簡潔にしてかつ饒舌なこのタイトルが作品のすべてを語っています。
シンメトリーの落ち着いた画面にまとめたこの人工の花は、お日様が昇り、陽光に照らされる時を待っている夜中のひまわりのようにスタティックでかつ圧倒的な存在感があります。
花火写真とは、光で描く生け花なのかも、などという連想も抱かせる、高い美意識でまとめられた名作です。
シンメトリーの落ち着いた画面にまとめたこの人工の花は、お日様が昇り、陽光に照らされる時を待っている夜中のひまわりのようにスタティックでかつ圧倒的な存在感があります。
花火写真とは、光で描く生け花なのかも、などという連想も抱かせる、高い美意識でまとめられた名作です。
過去の受賞作品
第65回(2024年)
第64回(2023年)
第60回(2019年)
第59回(2018年)
第58回(2017年)
第57回(2016年)
第56回(2015年)






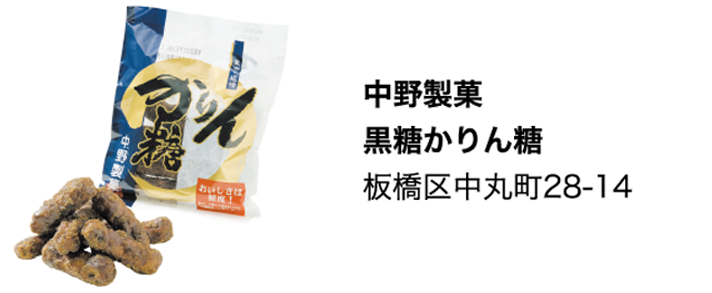


それぞれの人間模様はまるで巨大な花火の書き割りを前に演じられる群像劇のようにも見えます。
主催者としてはこの通路での観覧はお断りしているのですが、これだけの花火が目の前に上がれば、ひととき皆さんの足が止まるのも致し方なしかもしれません。
審査委員全員がグランプリに推した素晴らしい傑作です。